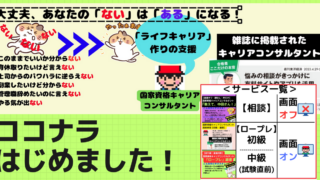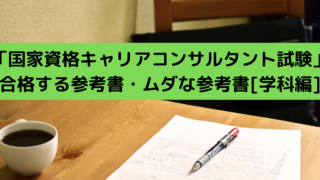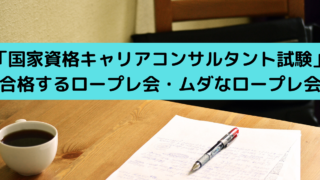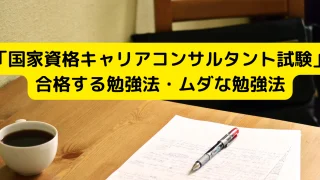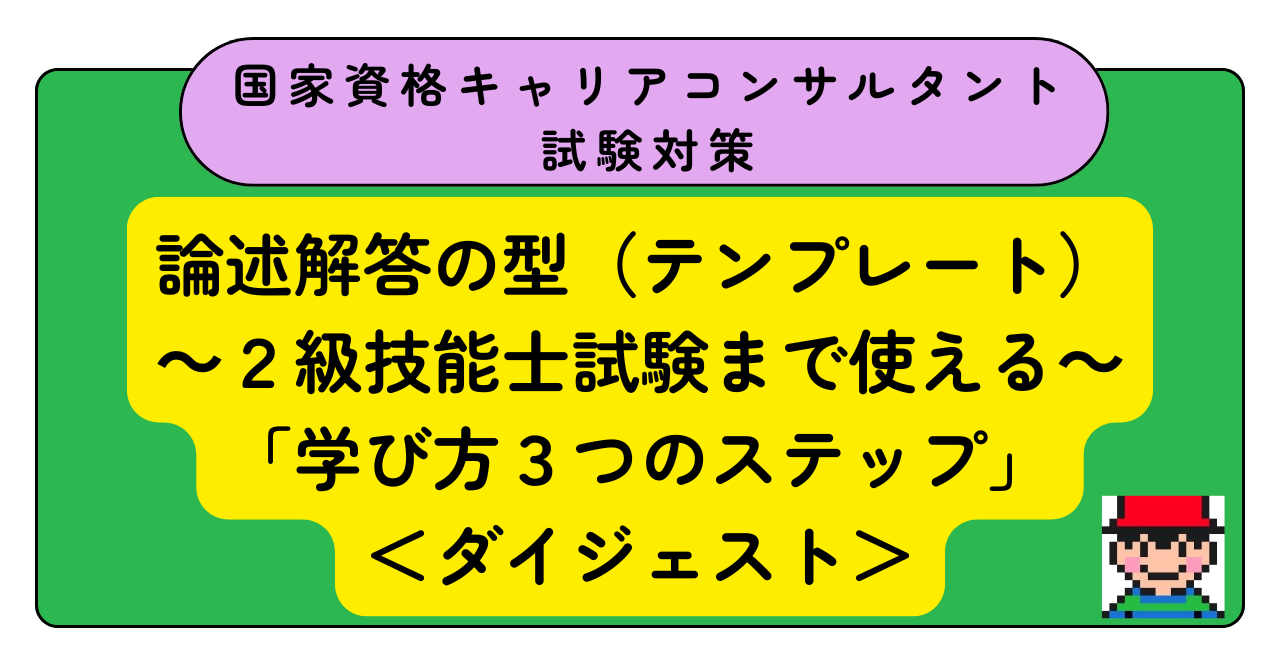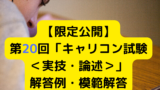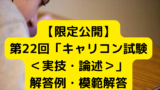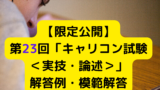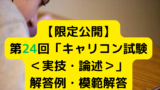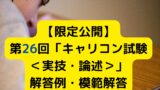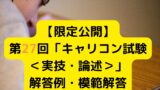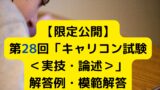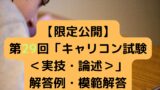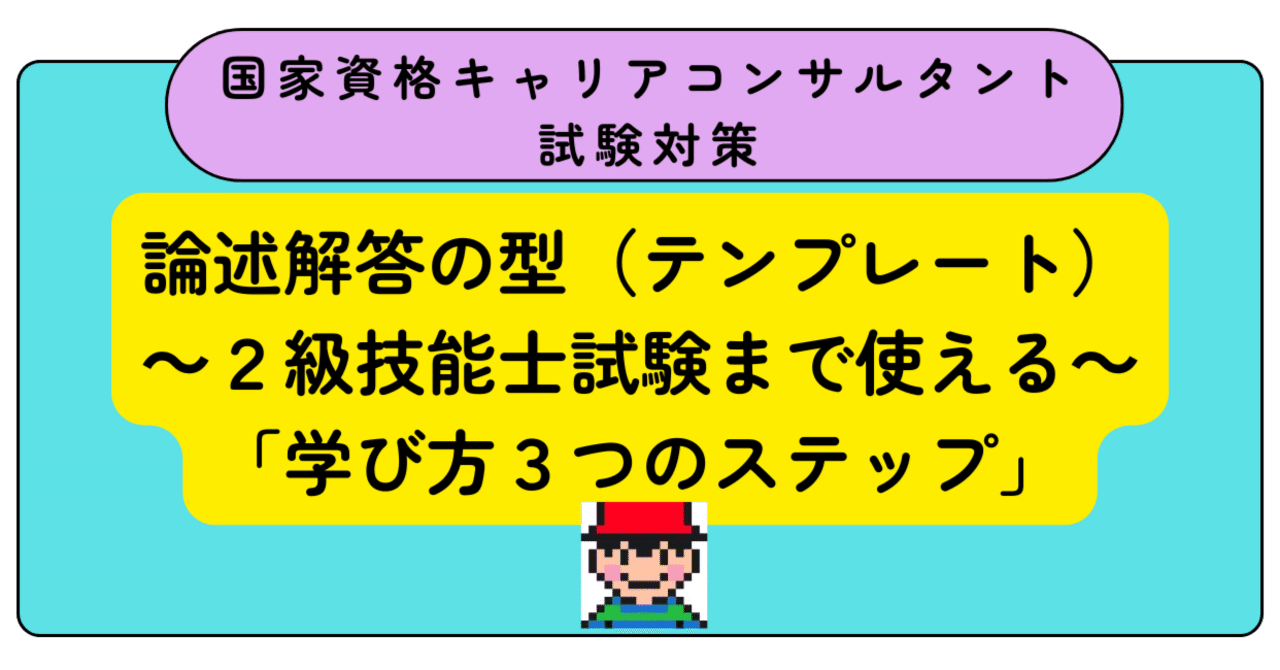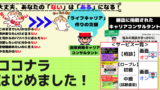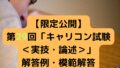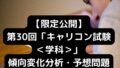論述対策はこんな感じで割と詳しく説明しています。
最近、よく聞かれるのが、
「論述はどうやって勉強してましたか?」
ということ。
これは、本当によく聞かれます。
ボクがキャリコン受験したときは第18回なので、論述対策の講座や本などもなく、いろいろ試しました。
同じ解答を採点してもらったら、ある人は90点だったのに、他の人は55点。
しかも、国家資格キャリアコンサルタントの資格保有者なのに、どうしてそこまでぶれるかってぐらい理解できず、迷走していました。
養成講座のオプションでも、ココナラの添削でも、本でも
いまは論述対策はかなり充実しています。
養成講座の有料のオプション講座もあれば、ココナラで添削してくれる人もいるし、本もたくさん出ていますね。
なので、お金の余裕次第と自分に合うものがあれば、それで勉強するのが一番だと思います。
もし2級技能士を目指すなら
ただし、もし、2級技能士を目指すのであれば、いまのうちから、
型(ひな形、フォーマット、テンプレート)
を作っておくと、あとが楽だったりします。
ボクがそうでしたから。
でも、いま考えると、どっかからパクってきたのではなく、「型」を自分で作ったことが結果としていろんなキャリコンの思考に触れることができつつ、自分に合う考え方をまとめることができたというその作業こそが、2級の受験に役立ったようにも思います。
分かるけど分からない「型」
この「型」についてですが、割と質問があり、伝えるのがけっこう難しかったりします。
で、極端な話、
「中田さんの型がほしい」
という方も割と多くいらっしゃいました。
それを一部の受験生には見せたことがあったのですが、見てようやくボクの伝えたいことが理解できたとおっしゃっていました。
多くの方は、それを見本にして、自分なりの型を作成しています。
まぁ、ボクのが見本としてふさわしいか分からないですが、それでも役に立つならばと思って、公開しようと思ったのですが、すでにお見せした受験生には、有料のレッスンで見せていたこともあり、今回は、noteの有料記事として公開しました。
今回も解説を加えて、解答例作成含めての所要時間はたったの20分程度。
他でも模範解答を掲載されているところがあると思いますが、良かったらそこと見比べて自分なりの解答を作ってみてください。
また、意図的にAIで解答を出すときの文字数は今回は少し多めにしていますので、必要に応じて、文字数の調整してみてくださいね。
最後に、ロープレの個別指導サービスをココナラではじめましたので、よかったらご利用ください。
来月が試験ということもあり、ワンコインを下回る480円で価格設定をしています。
(いつものお昼のお弁当をおにぎり1個に変えたと思って、そこで浮いたお金で買えるぐらいの金額設定にしています。)
テクニックに走るのも、悪くない
ボクは、テクニックに走るのも別に悪くはないと思っています。
テクニックだけだと困りますが、実際、ほとんどの受験生は、テクニックの習得+実践されていますから。
この実践がロープレの練習になるのですが、自分なりの型を持っている受験生はやはり安定しています。
「守破離」でいう「守」をテクニックと考えると、「破」は自分らしいキャリコンへの変化のようにも思います。
逆に、たまにいらっしゃるのが、初めから「破」からスタートして、すべて自己流だと、やはり試験なので、なかなか厳しいものがあります。
ただ、最近は、養成講座の先生が「破」からスタートするケースもあり、学校名は言いませんが、どん底まで自信喪失状態になっている受験生も多く、そういう意味では形からスタートするというのも悪くないのかなとちょっと思っています。
一番大切なのは、とりあえず過去問を制限時間で一度解くこと
論述の勉強をあまりしていないから、過去問を解かない方が割と多くいます。
しかし、そうだとしても、ボクは過去問は直近のでも良いので1回、制限時間内で解くことをお勧めします。
解答例はネットにたくさんあるので、逆に混乱してしまうかもしれませんが、2つ、3つ参考にすると、共通している用語を解答に入れていない場合、問題文の解釈がきちんとできていない可能性があります。
逆に、共通している用語はかけても、文字数が足りない、文字数が多すぎるといったこともあるかもしれません。そういった想定外のことをいまのうちに把握しておくことが特に大切です。
そこが弱点ですから、試験の1か月前(ギリギリでも3週間前)の土日の休日を使って克服することはきっとできると思います。
試験当日は緊張してしまうので、頭が真っ白になった場合、とりあえず、何か書くということで徐々に安心していきますので、そう意味でも、
「最悪、「型」があるから白紙はない」
というのもリスクヘッジとしてもっておくことをお勧めします。
勉強にはいろんなやり方がありますので、ボクの型じゃなくても、すでに、ネットでこの解答が分かりやすいなというのがあれば、それを写経して、そのロジックを自分のものにする、その考え方を突き通すっていうのもいいと思いますよ。
論述合格への3つのステップ
詳しくはnoteに記載していますが、論述で、合格ラインをギリ狙う場合、
ステップ1:解答の型(テンプレート)を作る
ステップ2:型(テンプレート)を覚える
ステップ3:問題文からキーワードを抜き出して、型(テンプレート)に埋める
これがベースとなります。
こちらのブログでは、それ以上の得点をゲットしてもらいたいので詳しく各回の論述について解説していますが、上にあるように
1回過去問を制限時間で解いてみて、ほとんど白紙でどうしていいか分からない
状態に陥ってしまったのであれば、3つのステップからスタートするのが良いと思います。