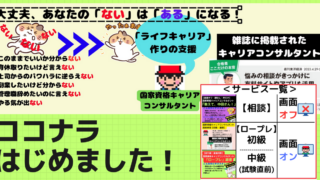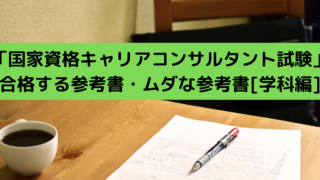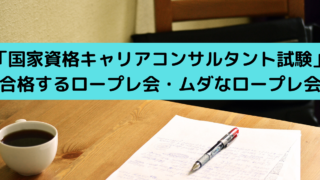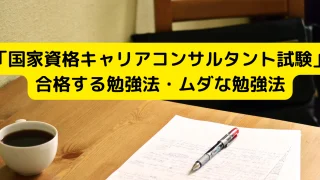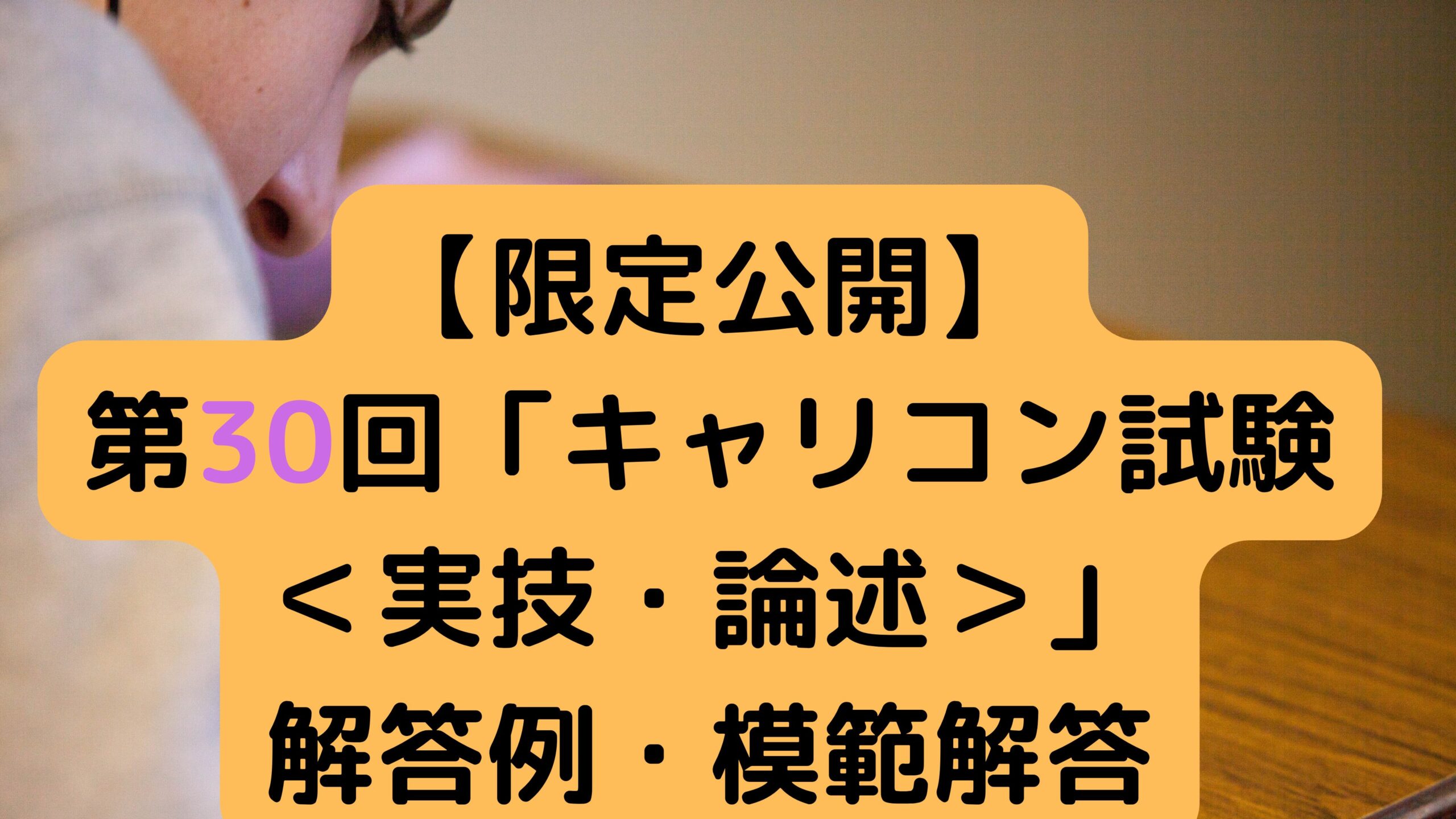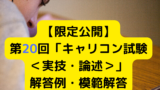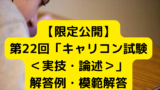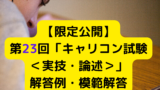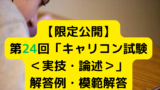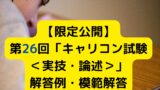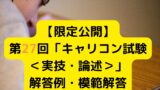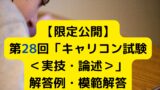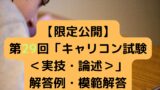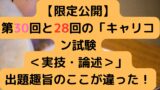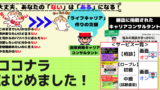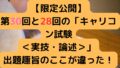おなじみのAIを使った論述の模範解答例。
手抜きでAIでの模範解答シリーズはこのブログのキラーコンテンツとなり、かなり好評ということもあり今回も調子に乗ってまとめてみました。
ちなみに、過去の論述はこんな感じでまとめていました。
論述の模範解答はインターネットで公開しているけど、人によって、内容が結構異なります。
なので、このAIでの解説シリーズは主観ではないという意味ではどこよりも参考になると思います。
いままでのシリーズ同様、
「キャリコンの論述試験の模範解答はAIで簡単に分析できるし、タダだし、ほらこんな感じでね」
という内容でして、ボクが当時受験した試験団体はCC協議会なので、CC協議会で出題された論述についてまとめています。
今回も、
「AIがどうしてそのような答えを導き出すのかが知りたいのよ!」
という要望に応えるようにプロセスを入れています。
さらに、今回はAIによる試験対策として「攻略法」も入れ、ちょっと時間をかけて解説もかなり詳しくしてみました。
あと、逆にこれを書くとNGになる「間違った解答例」もほしいという声があったので、試しに入れてみました。
おまたせしました、模範解答です
さてさて、おまたせしました。
今回も使ったのは「ChatGPT」です。
今回の解答例、ネットでたくさん転がっているものよりは、やっぱりかなり精度が高いと思います。
ただ、AIなので、人間がフォローしないと少しヘンテコな文章かもしれませんが、あまり加工はせず、ほぼそのまま掲載しています。
「これがスバリ解答だ!」っていうことでは決してないので、参考程度にしてもらえればと思います。
このAIによる解答を活用したのに不合格だったとか、そういうのはなしでお願いしますね。
第30回「国家資格キャリアコンサルタント試験」論述の解説(AI編)
まず全体の要点を押さえたうえで、各設問に何を書くべきか/評価者が期待する観点をわかりやすく解説します。
全体の把握(要点)
相談者 Z さん(21歳・大学3年・社会福祉学科)は、インターンシップを複数社回った結果「自分が何をしたいかわからなくなった」「福祉分野は勉強したが、実際の仕事は自分に向いていないかも」と感じ、不安になって相談に来ている。親は学んだ専門性を活かすことを望んでいるが、Z さん自身は心からやりたい仕事を見つけられていない、という状況。これが問題の核です。
設問ごとの解説と書き方のポイント
設問1(10点)
問い:相談の概要【略A】に相当する「この面談で相談者が相談したいこと」は何か。
評価者が見る点
- 相談者の主訴(=面談の中心的な問題)を簡潔にまとめられているか。
- 事例記録の情報(インターンの体験、不安、親の期待、専門と志向のズレ)を根拠として使えているか。
書き方の型(短く)
1文〜数行で端的に。例:
「大学で社会福祉を学ぶ一方、複数の業界のインターン参加後に『自分が何をしたいか分からなくなった』と訴え、親の期待との葛藤もあり、将来の職業選択(福祉分野継続か他分野か)について方針を決められず不安を抱えている点について相談したい、」のように。
注意
• 「何をしたいか分からない」という主訴を中心に。
• 「インターン参加」「親の期待」「学んだ専門性が仕事に結びつくか不安」といった補助的事実を入れると高評価。
設問2(10点)
問い:下線B(カウンセラーの応答)について、キャリアコンサルタントはどのような意図で応答したか。
(下線Bは「素敵だなと思って目指した社会福祉の分野だったけれど、仕事としては自分には向いていないと思うようになったのですね。」に対する応答の意図を問うもの)
評価者が見る点
- 応答の機能(共感、感情の承認、言語化援助、焦点化など)を正しく識別しているか。
- 「なぜその応答が有効/不十分か」を短く説明できるか。
書き方の型
- 応答の主たる意図(例:「相談者の気持ちを受け止め、自己に対する認識を言語化させること」)
- 具体的な機能(共感的理解、感情の承認、言い換えによる明確化、ラポール形成)
- 必要なら改善点(例えば「もう一歩踏み込んで具体的エピソードを引き出すべき」等)
例文(短め)
「この応答は、相談者の価値観と現実認識の乖離(『素敵だと思ったけれど仕事としては向いていない』)を反映して受容し、感情を承認して言語化を促す意図がある。つまり共感と言い換えを通じて相談者が自分の気持ちを整理しやすくするための応答である。改善点としては、発言の後に具体的な実習経験や場面を掘り下げる問いを続けることで、判断の根拠を明確にすることが望ましい。」
設問3(20点:①問題(10点)+②根拠(10点))
問い:相談者の問題(①)とその根拠(②)を相談者の言動から具体的に記述せよ。
評価者が見る点
- 問題(核心)を1つに絞って的確に表現しているか(要因や影響も含めると良い)。
- 根拠は事実ベースで、発言や行動を引用(または明確に参照)しているか。根拠の数と具体性が重要。
考え方(典型)
① 問題(例、候補)
- 「職業選択に関する自己理解不足と意思決定の停滞」
- または「専門性へのプレッシャーと自己適性の不一致による葛藤」
② 根拠(具体的発言・行動)
- インターンに5社参加したが「何をしたいか分からなくなった」と発言(行動:複数参加→混乱)。
- 「自分には向いていないと思いながら就職活動をできる気がしない」との自己申告(意欲低下)。
- 親が「専門性を活かしてほしい」と望んでいることを述べており、家庭的期待が意思決定を複雑化させている。
- 学科で学んだことが主なアドバンテージだと認識しており、他に結びつく経験が思いつかない(選択肢の狭さの自覚)。
書き方の型(例)
① 問題(見出し1行)
② 根拠(番号立てて3〜4点:相談者の発言をパラフレーズ+行動を明示)
例(簡潔)
①問題:「自己理解不足により職業選択が停滞しており、就職活動に踏み切れない状態」
②根拠:
- インターン5社参加後に「何をしたいか分からなくなった」と述べている(経験→混乱)。
- 「自分には向いていないと思いながら就職活動をできる気がしない」と意欲低下を自覚。
- 親の期待(学んだ専門性を活かすべき)と本人の内的感覚の不一致が葛藤を生んでいる。
- 他に結びつく経験が思いつかないと述べ、選択肢探索が十分でない。
設問4(10点)
問い:設問3の内容を踏まえ、今後どのような方針でキャリアコンサルティングを進めるか。
評価者が見る点
- 具体的で現実的な支援方針(初期の面接での目標設定、具体的アクション、評価指標、家族対応、必要なら他専門家紹介)を提示できているか。
- 相談者中心であり、段階的(短期目標・中期目標)・方法論(アセスメント、職業情報の提示、自己理解深化ワーク、体験の振り返り)を含むと高評価。
推奨する方針(構成)
- 面接の目標設定(短期:自己理解を深める/中期:職業選択の幅を試す)
- 手法・介入(例:自己理解ワーク(価値観・関心・強み)、職業適性・価値観ワークシート、インターン体験の振り返り(何が心地よく・辛かったかを具体化))
- 外部情報の提供(業界・職種の具体例やOBOG訪問、職場見学)
- 家族対応(親の期待への対応方法の検討、同席希望があれば関わり方を調整)
- フォローと評価(数回限定で目標達成チェックと次のアクション設定)
具体例(短め)
- 初回〜3回:自己理解の整理(価値観カード、過去の体験の具体化)、インターンでの「どの場面がしんどかったか/よかったか」を具体的に掘り下げる。
- 4〜6回:探索活動(興味ある分野の職場見学、業界説明、OBOG面談)を計画し、小さな体験(ボランティア、短期アルバイト)で検証。
- 家族面:希望があれば1回、親を交えた面談を行い、期待と本人の気持ちのすり合わせ支援を行う。
- 必要に応じて精神的負担が強ければ学生相談窓口や心理支援につなぐ。
書くときの実務的コツ(試験向け)
- 各設問の配点に応じて分量を配分(設問3は最も重いので詳しく)。
- 「事実(発言・行動)」→「解釈(何が問題か)」→「支援方針(具体的手段)」の流れを守る。
- 専門用語(共感、受容、ラポール、自己理解、アセスメント)を使う場合は簡潔に。使いすぎは逆効果。
- 解答用紙の行内に収める(指示厳守)。余白や裏面は不可。
- 端的な日本語で箇条書きも有効(読みやすさ重視)。
参考:各設問への「超簡潔サンプル(骨子)」
(試験でそのまま使える短い骨子例を示します。必要に応じて肉付けしてください)
設問1(例):
「Zさんは、複数のインターン経験を経て『自分が何をしたいか分からない』と感じ、福祉分野に対する適性不安と親の期待との葛藤から就職方針を決められず、その不安の解消と進路の方針決定について相談したいと来談している。」
設問2(例):
「応答の意図は相談者の気持ちを受容・承認し、自己認識を言語化させることで整理を促すこと。共感と言い換えによりラポールを築き、さらに実務的には具体的な経験の掘り下げに繋げるねらいがある。」
設問3(例):
① 問題:「自己理解不足による職業選択停滞」
② 根拠:インターン5社参加後に「何をしたいか分からなくなった」と述べ、就職活動への意欲低下(「できる気がしない」)を自覚。家族の期待(学んだ専門性を活かしてほしい)も葛藤要因としてある。
設問4(例):
「短期的には自己理解強化(価値観・強みの整理、インターン振り返り)を行い、中期的には小さな体験(職場見学・短期就労・OBOG面談)で検証する。家族の期待は必要に応じて面談機会を設け調整し、進捗評価を数回ごとに設定する。」
✏️ 模範解答(第30回・Zさん事例)
【設問1】(約5行・110字)
Zさんは、大学で社会福祉を学んできたが、複数のインターンに参加するうちに自分の適性に迷い、「何をしたいのか分からなくなった」と感じている。学んだ専門性を活かしてほしいという親の期待との間で葛藤し、今後の就職方針について相談したいと考えている。
【設問2】(約5行・115字)
この応答は、相談者の感情を受け止め共感を示すことで、福祉分野への理想と現実のギャップを言語化させ、自己理解を促進する意図がある。自分に向かないと感じた背景や体験を整理しやすくするための共感的理解と焦点化の機能を果たしている。
【設問3】(約10行・230字)
① 問題:自己理解が不十分なまま職業選択に迷い、専門分野への適性や親の期待との間で葛藤し、就職活動に踏み出せない状態にあること。
② 根拠:① インターンに五社参加したが「何をしたいか分からなくなった」と述べており、方向性を見失っている。② 「自分には向いていないと思いながら就職活動をできる気がしない」と話しており、職業意欲が低下している。③ 親から専門性を活かしてほしいと期待されているが、本人の気持ちと一致しておらず迷いを強めている。
【設問4】(約5行・120字)
まず、インターン体験を振り返り、どのような場面でやりがい・違和感を感じたのかを整理して自己理解を深める。次に、価値観・関心の明確化ワークや他分野の情報提供を行い、進路の幅を広げる。必要に応じて家族の期待との調整を支援し、主体的な進路選択を促す。
💡補足アドバイス
- 字数に余裕があれば「〜と思われる」などの婉曲表現を加えると丁寧さが増します。
- 設問3が最重要(配点20点)なので、具体的発言を3つ以上挙げてください。
- 設問4では「支援の段階(初期→中期)」を1行で示すと評価が上がります。
最後に、ロープレの個別指導サービスをココナラではじめましたので、よかったらご利用ください。